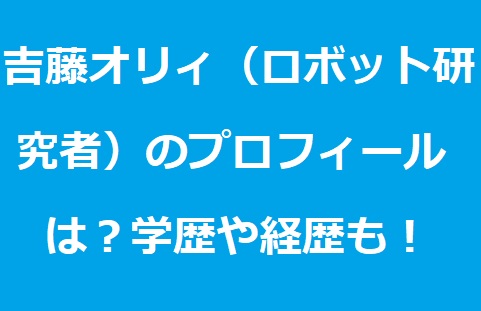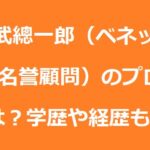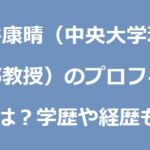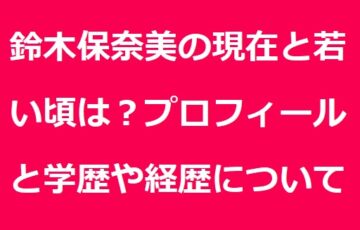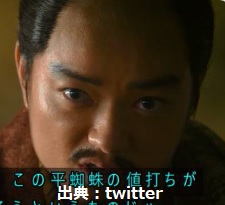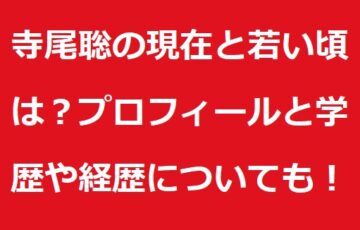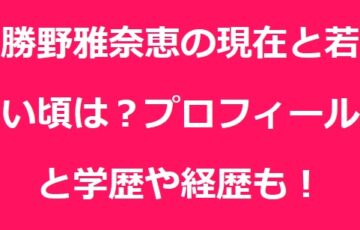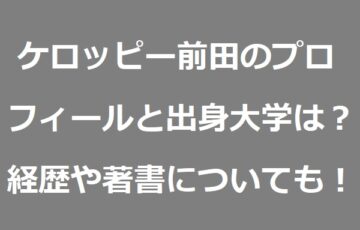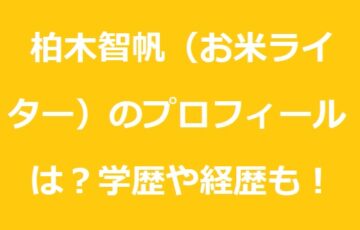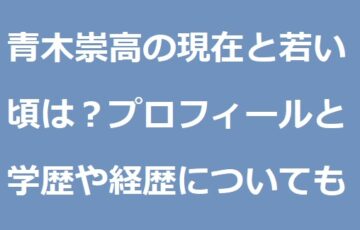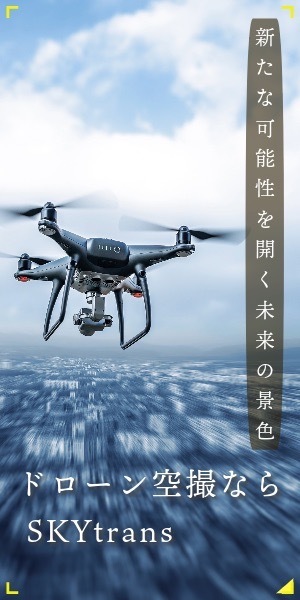5月17日の「所さん!事件ですよ」に吉藤オリィさんが出演!
吉藤オリィさんってどんな人なのか気になり調べてみました。
今回は、『吉藤オリィ(ロボット研究者)のプロフィールは?学歴や経歴についても!』
と言うタイトルで、吉藤オリィさんについてお伝えしたいと思います。
どうぞ最後までごゆっくりお読みください。
Table of Contents
吉藤オリィ(ロボット研究者)のニュース

出展:ボンボン堂
所さん!事件ですよ 夜中にクレーンゲームが大暴走!?
夜中に大量のクレーンゲームが勝手に動き出す工場がある!?
人手不足に悩む建設現場でゲーマーが救世主になるかもしれない!
?ロボットの遠隔操作で働き方革命
5月17日 土曜 18:05 -18:34 NHK総合1・東京
番組内容
夜中に大量のクレーンゲームが勝手に動き出す工場がある!?
衝撃の情報をもとにディレクターが向かった埼玉県の工場に広がっていた驚きの光景とは?
所さんもびっくり!人手不足に悩む建設業界でゲーマーが救世主になるかもしれない!?。
「それでも私は働きたい」ー難病患者の女性が分身ロボットで働くカフェに
外国人観光客が殺到!
ロボットの遠隔操作で働き方革命がおこっている令和のニッポンのいまを深掘り。
出演者
【司会】所ジョージ,木村佳乃,
【ゲスト】中央大学 理工学部教授…國井康晴,
ロボット研究者…吉藤オリィ,キンタロー。,
【語り】吉田鋼太郎
引用:「所さん!事件ですよ」番組案内から
吉藤オリィ(ロボット研究者)のプロフィール

出展:早稲田大学
- 名前:吉藤 オリィ(本名:吉藤 健太朗)
- 生年月日:1987年11月18日(37歳)
- 出身地:奈良県北葛城郡新庄町(現・葛城市)
- 最終学歴:早稲田大学創造理工学部卒
- 職業:ロボット研究者、起業家
- 所属:株式会社オリィ研究所 代表取締役/デジタルハリウッド大学大学院 特任教授
- 代表作:分身ロボット「OriHime」、分身ロボットカフェ「DAWN」
2025年5月17日放送のNHK『所さん!事件ですよ』に、
ロボット研究者・吉藤オリィさんが出演しました。
この日のテーマは「孤独に寄り添うテクノロジー」。
番組では、高齢化や長期療養などによって社会とのつながりを絶たれてしまう人々に対し、
「ロボット技術でつながりを生む」最前線の取り組みを紹介。
その中心にいたのが、“分身ロボットOriHime(オリヒメ)”の開発者・吉藤オリィ氏です。
スタジオでは、吉藤さんが「孤独は感情ではなく、状態です」と語り、
テクノロジーによって“孤独を解消する”という視点の重要性を丁寧に解説。
とりわけ、外出できない人が遠隔で働ける「分身ロボットカフェDAWN」の事例は、
多くの反響を呼びました。
吉藤オリィ(ロボット研究者)の経歴

出展:YouTube
吉藤オリィさんは、自らの不登校・孤独の経験を原点に、「孤独を解消する」ことを人生のミッションとしてロボット開発に取り組む、稀有なロボット研究者・社会起業家です。その活動は工学、福祉、ビジネス、教育、メディアなど多分野にまたがり、国内外から高く評価されています。
幼少期〜不登校、そして“孤独”との出会い
吉藤さんの人生を大きく変えたのは、小学5年生の頃、体調不良による入院をきっかけに始まった不登校とひきこもりの生活です。3年半という長い期間、家庭にこもり、人との関わりを絶たれた中で感じたのは、「孤独」の痛みでした。
この時期に出会った折り紙やロボット工作が、彼にとっての“自己表現の手段”となり、次第に「技術で人とつながりたい」という思いが芽生えていきます。
ひとつの転機となったのが、母親が応募した「虫型ロボット競技大会」への出場。中学1年で出場したこの大会で優勝を果たし、翌年の全国大会で準優勝。この経験が、自信と目標を彼に与えました。
高校時代:再び社会とつながるための挑戦
不登校からの復帰を決意した吉藤さんは、奈良県立王寺工業高等学校を目指し猛勉強。合格後は、憧れの教師・久保田憲司氏のもとで研究活動に取り組みます。
高校時代には「傾かず段差を登れる電動車椅子」を開発し、文部科学大臣賞、Intel ISEF(国際学生科学技術フェア)グランドアワード3位と、世界的な評価を受けました。
この頃から彼は、単なるものづくりを超えて、「技術で誰かの生き方を支える」というビジョンを持つようになります。
また、技術に惚れ込んだ高齢者たちから「こういうのを作ってほしい」と直接相談されることも多くなり、“人の声”をきっかけに技術を生み出すスタイルが形成されていきました。
大学時代:人工知能から“分身ロボット”へ
高専へ進学後はAIパートナーの研究に着手しますが、「AIでは孤独を完全に解消できない」と限界を感じ、人間と人間をつなぐ“通信”に重きを置いた方向へと転換。
早稲田大学創造理工学部へ編入し、自主的に「オリィ研究室」を設立。分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」の研究開発に取り組みます。
資金がなかったため、他研究室のゴミから部品を拾って試作し、生活費や奨学金を全てロボット開発に注ぎ込みました。アルバイトも辞め、ビジネスコンテストの賞金だけで生活と研究をまかなっていたといいます。
当初は「AIも搭載していないのにロボットと呼べるのか?」という批判にもさらされましたが、あえて「分身ロボット」という新しい概念を提唱。「機械に“なってくれる”誰かがいる」ことで、人と人がつながる手段としてのロボットを明確に打ち出しました。
起業:オリィ研究所とOriHimeの実用化
2012年、株式会社オリィ研究所を設立。最初の製品は、ALSなどで話すこと・動くことが困難な人々が視線入力で遠隔操作できる「OriHime eye + switch」。厚生労働省認定の福祉機器としても登録され、医療・介護現場でも活用が広がりました。
その後、全長120cmの「OriHime-D(オリヒメディー)」を開発。このモデルは、外出困難な人がロボットを通じてリアルな場に“存在”し、働く・会話する・接客するといった社会活動を可能にするもので、テレワークの新しい形を実現しています。
2018年には、寝たきりの人が接客できる「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」を日本財団との共同で期間限定オープンし、大きな話題に。
2021年にはクラウドファンディングで4,500万円以上を集め、常設の「分身ロボットカフェDAWN」が誕生。現在もパイロット(ロボット操作者)として、全国各地の難病・障がい当事者が勤務しています。
社会へのメッセージと今後の展望
吉藤オリィさんの活動は、単に「便利なロボットを作る」という技術開発ではなく、“孤独の社会構造そのもの”を変えることを目的としています。
彼が強調するのは、孤独は感情ではなく「状態」であり、それを技術で“解消”できる可能性があるという視点。だからこそ、ロボットに必要なのは知能よりも「存在」であり、感情よりも「関係性」だと語ります。
また、ALS患者や重度障がい者たちと開発・実証を共に行う「オリィの自由研究部(β)」を結成し、障がい当事者とともに未来を創る開発プロジェクトを進行中。
将来的には、在宅での就労支援・教育・医療・文化活動など、あらゆる場面で“分身ロボット”が活躍する社会の実現を目指しています。
このように、吉藤オリィさんの経歴は、「孤独」という個人的課題から出発し、社会規模のソリューションへと昇華された類まれな実践の軌跡です。
テクノロジーの使い道を「人の痛みを埋めるため」と明確に定義して行動してきた彼の生き方は、多くの人にとって、希望そのものといえるでしょう。
吉藤オリィ(ロボット研究者)のXの反応
このあと18時5分から放送! https://t.co/59QReHtkkN
— 吉藤オリィ@分身ロボット研究者 (@origamicat) May 17, 2025
盛岡に来た! https://t.co/DPbdxIeOFa
— 吉藤オリィ@分身ロボット研究者 (@origamicat) May 16, 2025
寝たきり状態であったり身体が不自由であっても、生身で行くと18時間くらいかかる地球の裏側に瞬間移動し、接客仕事ができ、人と出会える時代 https://t.co/BttkRB77rd
— 吉藤オリィ@分身ロボット研究者 (@origamicat) May 14, 2025
車椅子を魔改造する本気のメンバーを集めた!#オリィ部 https://t.co/IQVS7BcQhq
— 吉藤オリィ@分身ロボット研究者 (@origamicat) May 14, 2025
7年の友人のALS患者のみかさんに「車椅子に仲間と会う時に握手や乾杯ができるアームが欲しい」と言われ、開発したところ同窓会で使ってくれた
ALSになっても絵を描き続けバリスタを続けるみかさんには本当色々教わっている#車椅子には腕が足りない https://t.co/S4enxpQTjH pic.twitter.com/Tl1hinv5D1— 吉藤オリィ@分身ロボット研究者 (@origamicat) May 7, 2025
こちらの記事も読まれています!
吉藤オリィ(ロボット研究者)のまとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、『吉藤オリィ(ロボット研究者)のプロフィールは?学歴や経歴についても!』
と言うタイトルで、吉藤オリィさんについてお伝えしました。
吉藤オリィさんは、ロボット技術を通じて「孤独を解消する」という社会的課題に挑む、
唯一無二の存在です。
不登校やひきこもりという原体験を原動力に変え、
分身ロボットOriHimeの開発を通じて“誰もが社会とつながれる世界”を形にしてきました。
「テクノロジーは、人の痛みに寄り添うもの」という信念のもと、
開発・教育・啓発に力を注ぐ吉藤さんの活動は、まさに未来をつくる挑戦です。
これからも、オリィ研究所と吉藤オリィ氏の歩みに注目が集まります。
今回も最後までお読みいただき有難うございました。