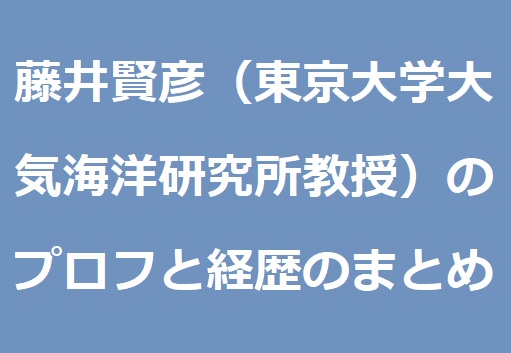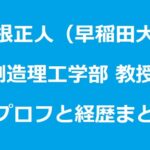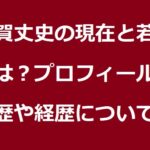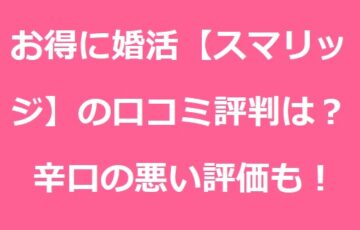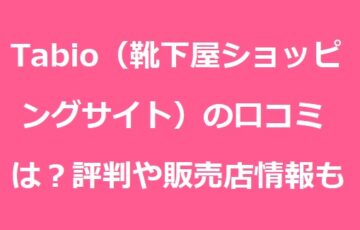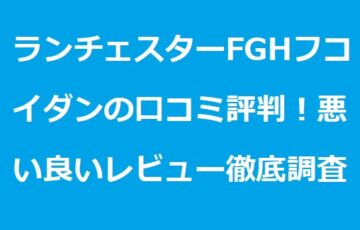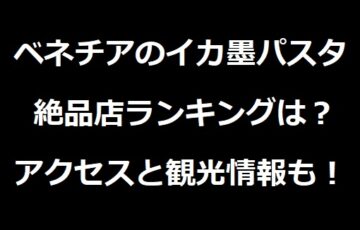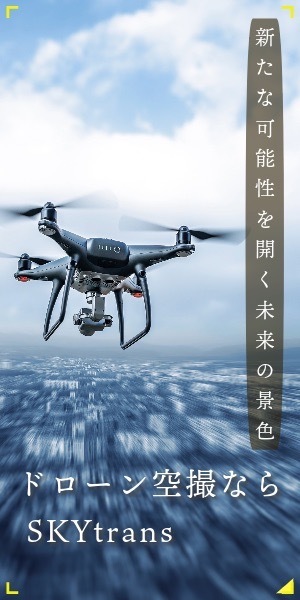Table of Contents
藤井賢彦 プロフィール・経歴まとめ(東京大学 大気海洋研究所 教授)
プロフィール
-
名前(よみ):藤井 賢彦(ふじい まさひこ)
-
職名・所属:
-
東京大学 大気海洋研究所 教授(2023年4月より)
-
東京大学 附属国際・地域連携研究センター 教授(兼務)
-
-
学位:博士(地球環境科学/北海道大学、2001年)
-
専門分野:海洋酸性化・地球温暖化・貧酸素化・沿岸モデル/緩和策と適応策の統合的評価
経歴:国際フィールド研究から東京大学へ
初期キャリア(〜2008年)
-
1996年:九州大学理学部を卒業
-
2001年:北海道大学大学院 地球環境科学研究科博士後期課程修了(博士号取得)
-
2002年〜2005年:国立環境研究所特別研究員、その後米国・メーン大学にて博士研究員として海洋科学研究に従事
北海道大学 准教授時代(2006〜2023年)
-
2006年:北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター 特任准教授に就任
-
2008年から2023年3月まで、同大学地球環境科学研究院 准教授として研究室を率いる
-
この間、国内外で海洋モデリングおよび環境影響評価の先駆的研究に従事(北海道沿岸域、東京湾など)
国際経験:訪問・客員研究(2013〜2022年)
-
2013年:トリノ工科大学 客員教員として滞在
-
2022年:ワシントン大学 Visiting scholarとして研究交流を果たす
️ 東京大学 教授就任(2023年〜現在)
-
2023年4月より、東京大学 大気海洋研究所および国際沿岸海洋研究センターにて教授に就任
-
岩手県大槌町の研究センターを拠点に、沿岸環境の継続観測と地域密着型モデリング研究を推進中
主な研究テーマと成果
海洋酸性化と貧酸素への環境モニタリング
-
北海道の亜寒帯沿岸において、海水酸性化と酸素濃度の変動を高頻度で測定。CO₂濃度上昇による水質低下の影響を地域スケールで把握
-
未来予測では、海洋酸性化によりホタテやアワビなどの殻形成に影響が出る可能性が示され、温暖化リスク評価にも貢献
高解像度生態系モデル(CROCO + PISCES)
-
宮古湾や志津川湾などの海域で、地域密着型モデリングによる海洋酸性化×貧酸素化の複合影響評価を実施
-
RCP8.5シナリオを用いた将来予測では、Ωₐᵣₐ(飽和状態)が年間を通じて臨界閾値を下回り、幼生や貝類への深刻な影響が予測される
貝類養殖と生態系影響評価
-
岡山・宮城地域のマガキ養殖場で海水温やpH、DO変動の現場観測を実施。成長リスクや漁業的影響を数理モデルで評価
-
被災地支援に向けた地域連携型研究も活用されており、漁業や食産業との接点が強い成果を提供
緩和策・適応策の政策提言
-
国際機関 IMBeR や GOA‑ONの委員として、海洋酸性化問題への国際的対応に参画
-
「日本のOAアクションプランの必要性」に言及し、政策連携の強化を提言するなど、科学と社会の橋渡しにも取り組む
著作と学術功績(2023〜2024年度)
-
主要査読論文(with 川合・石津ほか、2024年):日本沿岸域における酸性化の現状評価(『地球環境』29巻1号)
-
2023年論文:岡山・宮城での養殖貝類研究などによる温暖化・酸性化の影響評価(Biogeosciences)
-
2023年 CROCO モデル研究:沿岸生態系モデル開発による貝類の将来予測(Frontiers in Marine Science)
-
その他、酸性化適応やエネルギー政策連携に関する論文・政策提言を多数執筆
社会・行政との連携と今後の展望
-
日本学術会議・国際UNESCO・IMBeR委員として、環境政策立案や行動戦略策定に関与
-
2025年日本地球惑星科学連合大会で岩手沿岸のCO₂湧出に関する研究発表予定
こちらの記事も読まれています!
総まとめ:藤井賢彦教授とは?
藤井賢彦先生は単なる研究者ではなく、海洋環境問題の“場に寄り添う”科学者です。国内外を跨いで長期観測と精密モデルを駆使し、沿岸生態系と社会の未来を見通す研究を実践。講演・政策提言・地域連携を通じて、研究成果を形に変える力を持った研究者です。
地球温暖化や酸性化、その社会的影響に関心を持つ方には、論文や報告のみならず、公開講演や社会連携活動にも注目です。藤井教授の今後の動向は、海と人、地域と世界を繋ぐ学際的研究の指標となるでしょう。