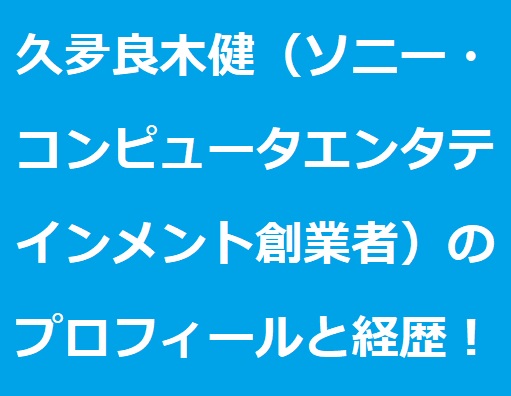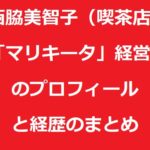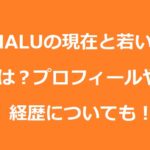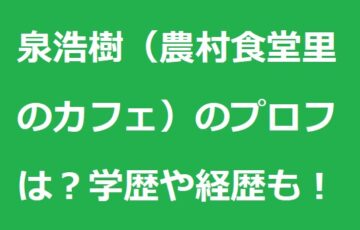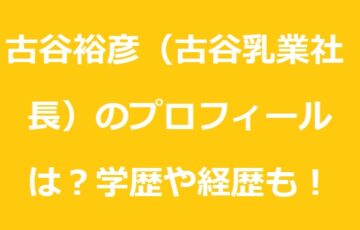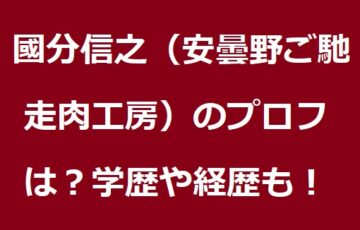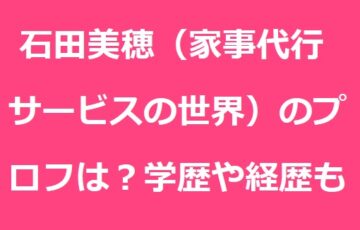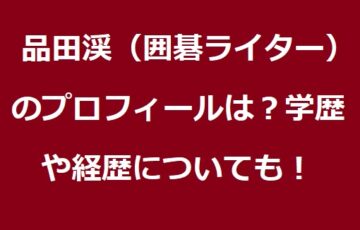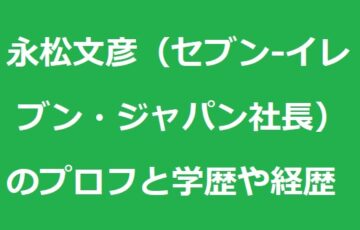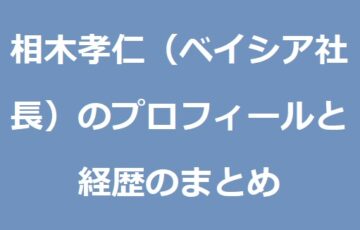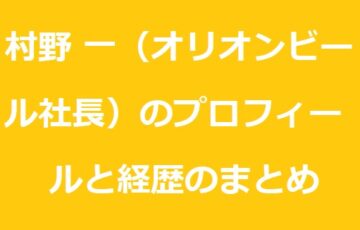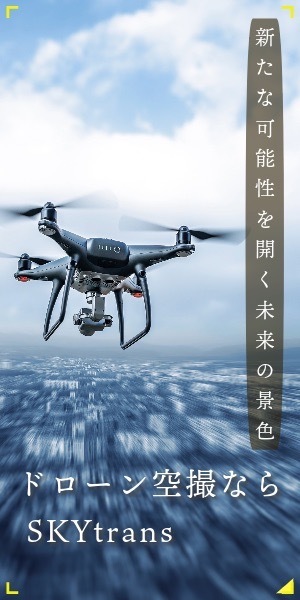Table of Contents
久夛良木健のニュース
 出典:ファミ通
出典:ファミ通
2025年10月11日放送のNHK『新プロジェクトX~挑戦者たち~』では、
「世界を変えたゲーム機開発劇」として、ソニー・コンピュータエンタテインメントの
初代社長・久夛良木健(くたらぎ けん)さんが取り上げられました。
番組では、家庭用ゲーム機「PlayStation(プレイステーション)」誕生の舞台裏に迫り、
久夛良木さんがいかにして社内の反対を押し切り、
世界市場を制する革新的なハードを生み出したのかが描かれました。
「ゲームを大人のエンターテインメントに」という信念のもと、
3Dグラフィックス技術を導入して臨場感あふれる映像表現を実現。
番組では、ソニー社内の葛藤、半導体開発チームとの運命の出会い、
そして世界中を熱狂させた発売当時の反響などが、
貴重な映像や関係者インタビューとともに紹介されました。
久夛良木健のプロフィール

出典:JBpress
名前:久夛良木健(くたらぎ けん)
生年月日:1950年8月2日(75歳)
出身地:東京都
最終学歴:電気通信大学卒業
職業:実業家・技術者(ソニー・コンピュータエンタテインメント創業者)
久夛良木健の経歴
 出典:ダイヤモンド・オンライン
出典:ダイヤモンド・オンライン
ソニー入社と電子技術者としての出発
久夛良木健さんは1950年、東京都に生まれました。電気通信大学で電子工学を学び、1975年にソニーへ入社。
当初はオーディオ関連の回路設計を担当し、音響技術や半導体設計の基礎を学びます。
社内では若手ながら強い探究心を持ち、従来の常識にとらわれないアイデアを数多く提案しました。
任天堂との共同開発と幻の「プレイステーション」
1980年代後半、久夛良木さんは任天堂との共同開発プロジェクトに参加。
CD-ROMを搭載したスーパーファミコンの拡張機構を開発していましたが、契約上の対立によりプロジェクトは中止。
しかしこの出来事が、後に独自の家庭用ゲーム機「PlayStation」構想へとつながります。
「ゲームは子どもだけのものではない。大人も夢中になれるエンターテインメントにする」という彼の信念が、社内外で異端視されながらも、少数精鋭チームによる挑戦を生み出しました。
PlayStationの誕生と世界的成功
1994年、久夛良木さん率いるソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)は、初代PlayStationを発売。
3Dポリゴン技術と高性能CPUを採用した革新的なゲーム機は、世界中で大ヒット。
発売1年で全世界の出荷台数が200万台を突破し、ゲーム産業の勢力図を塗り替えました。
久夛良木さんは「エンタメを次の産業に育てる」ことを掲げ、ハードだけでなくソフト開発環境や流通構造まで改革。
ゲーム産業を、映画や音楽と肩を並べる文化へと押し上げました。
プレイステーション2~3への進化と経営者としての手腕
2000年にはPlayStation 2を発売。DVD再生機能を搭載し、家庭のエンタメ中枢として世界的成功を収めます。
その後も久夛良木さんはPlayStation 3の開発に着手し、独自CPU「Cell Broadband Engine」の開発を主導。
エンジニアとしての高い理想と先見性を持ち、ゲームを超えた情報処理プラットフォームの実現を目指しました。
2007年にソニー退社後は、デジタル技術の研究や教育支援に携わり、技術者の育成に力を注いでいます。
技術者としての哲学と挑戦
久夛良木さんの開発哲学は「誰もやらないことをやる」。
リスクを恐れず、新しい市場を切り開く姿勢は、現在のクリエイターにも多大な影響を与えました。
番組内では「反対されるほど燃えるタイプ」と語る関係者の証言も紹介され、久夛良木さんの情熱と信念がいかにPlayStationを成功へ導いたかが浮き彫りになりました。
久夛良木健のXの反応
「まさに“異端の技術者”という言葉がぴったり」
「久夛良木さんの信念が世界を変えた。胸が熱くなった」
「当時のソニー社内の空気がリアルに伝わってきた」
「ゲーム史の裏側を知れて感動。プロジェクトXらしい回だった」
久夛良木健のまとめ
久夛良木健さんは、常識に挑み、世界のエンターテインメントの在り方を変えた技術者です。
『新プロジェクトX』では、PlayStation誕生までの苦闘と情熱、
そして“夢を現実にした男”の生き様が丁寧に描かれました。
彼の「大人も楽しめるゲームを」という理念は、
今も世界中の開発者やファンに受け継がれています。
技術と信念が融合した挑戦の物語は、令和の今も色あせることなく、
多くの人に勇気を与えています。
出典
・NHK『新プロジェクトX~挑戦者たち~』(2025年10月11日放送)
・ソニーグループ公式サイト
・日経クロステック
・毎日新聞デジタル
・電気通信大学OBインタビュー