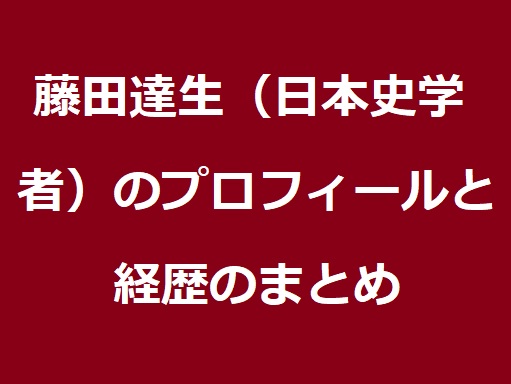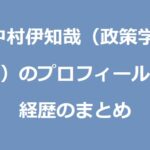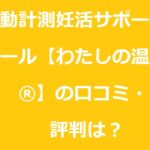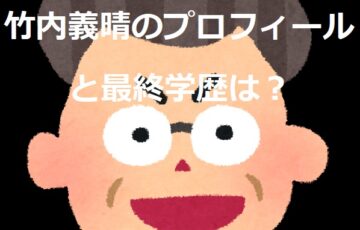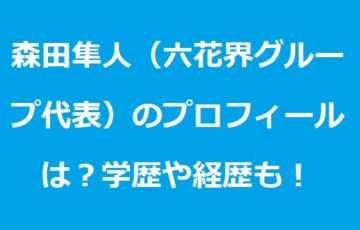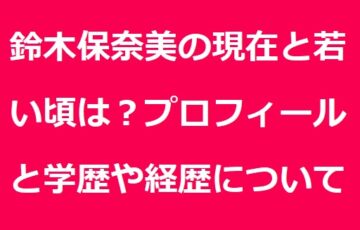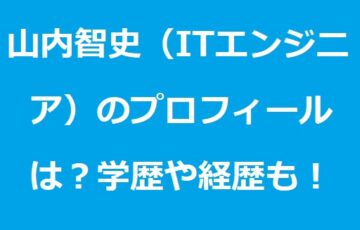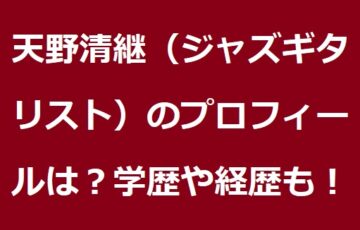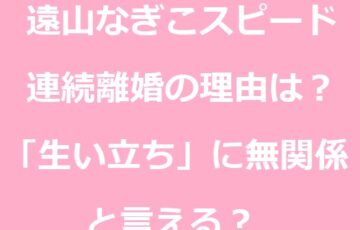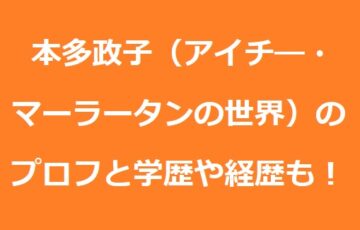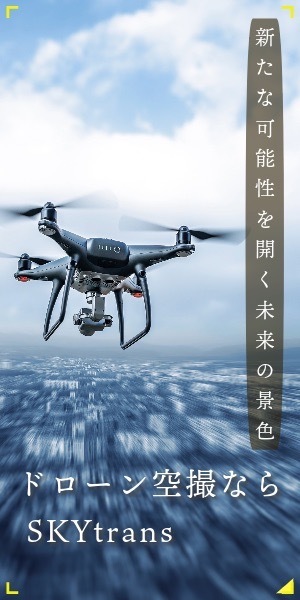Table of Contents
藤田達生のニュース
 出典:NHK ONE
出典:NHK ONE
2025年10月28日(火)放送のNHK・Eテレ「先人たちの底力 知恵泉」に、
歴史学者の藤田達生(ふじたたつお)さんが出演します。
今回のテーマは「豊臣秀吉 天下統一への知恵」。
戦国から安土桃山へと移り変わる時代に、
どのようにして人々が社会の仕組みを作り上げたのかを、藤田さんがわかりやすく解説します。
藤田さんは、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康に連なる「織豊政権」期の政治構造や城下町形成を
専門とする研究者。
城や藩制度、地域支配の実態を丹念に掘り下げる学風で知られ、
戦国時代研究の第一人者として数多くのテレビ番組・講演会にも登場しています。
今回の放送では、秀吉の「土木力」や「人心掌握術」など、
歴史の裏側に潜む知恵を現代に重ね合わせ、未来を見通すヒントを提示します。
藤田達生のプロフィール
 出典:三重県総合文化センター
出典:三重県総合文化センター
名前:藤田達生(ふじた たつお)
生年月日(年齢):1958年10月8日(66歳)
出身地:愛媛県新居浜市
最終学歴:神戸大学大学院博士課程修了(博士・学術)
職業:三重大学名誉教授、歴史学者
藤田達生の経歴

出典:三重大学
学生時代と研究の出発点
愛媛県新居浜市に生まれ育ち、幼少期から歴史への関心が強く、地元の郷土史にも深い興味を抱いていました。
1977年に愛媛大学教育学部に入学し、社会科教育を専攻。卒業後は「地域から日本史を見直す」という視点で研究を志すようになります。
その後、神戸大学大学院に進学し、「日本中世における地域的権力の研究—近江国を事例として—」をテーマに博士論文を執筆。
1987年に博士(学術)を取得し、日本史学の新しいアプローチとして「地域権力と中央政権の関係性」を提示しました。
三重大学での教育・研究活動
1987年に神戸大学助手として学究の道を歩み始め、1993年に三重大学教育学部助教授に就任。
以降、教育と研究の両立を重視し、学生と共に現地調査や史料分析を行う「実証的歴史学」の手法を確立します。
2003年に同大学教授、2015年からは大学院地域イノベーション学研究科でも教鞭を執り、地域社会と歴史研究を結びつける教育を推進しました。
2024年には三重大学を定年退任し、現在は同大学名誉教授・特任教授として研究活動を続けています。
研究テーマと業績
藤田さんの研究分野は「日本近世国家の成立史」。特に、戦国から江戸初期にかけての「織豊期(しょくほうき)」と呼ばれる時代を中心に、
城郭・城下町・藩体制などの制度史を再構築しました。
従来の“合戦中心の戦国史観”を超え、信長や秀吉が行った社会構造の変革に注目し、「戦国を終わらせた仕組みづくりの時代」として位置づけたことが特徴です。
この研究スタイルは「歴史を政治と建設の両面から読む」独自の視点として高く評価されています。
代表的な著書には、『秀吉と海賊大名』『信長革命』『天下統一とは何か』『織豊政権と地域支配』などがあり、
戦国時代を「日本近代国家の原点」として見直す論考を発信し続けています。
社会への発信とメディア出演
研究だけでなく、一般向けの講演やテレビ出演にも積極的で、NHK「歴史探偵」「知恵泉」「ブラタモリ」などに数多く出演。
専門的な史料分析を一般視聴者にも伝わりやすい形で紹介し、歴史ファンからの信頼も厚い存在です。
また、地域の文化遺産保全や観光資源化にも関わり、地元自治体との共同プロジェクトにも携わっています。
藤田達生のXの反応
「戦国を“つくる力”から読み解く藤田先生の視点が面白い」
「秀吉=土木と政治、まさに知恵泉にぴったりのテーマ」
「藤田先生が出る回はいつも深掘りがすごい。録画必須!」
「歴史を“生きた社会の構築”として見せてくれる数少ない学者」
藤田達生のまとめ
藤田達生さんは、戦国から近世への転換期を「国家形成の過程」としてとらえる歴史学者です。
その研究は単なる過去の記録ではなく、現代社会の構造や組織運営に通じる“知恵”を提示するもの。
今回の「先人たちの底力 知恵泉」では、豊臣秀吉の知略と政策を通じて、
“乱世を収める仕組みづくり”というテーマを掘り下げます。
学術的知見と人間的洞察が交差する、見ごたえのある回となりそうです。
こちらの記事も読まれています!
出典
・NHK「先人たちの底力 知恵泉」番組情報
・三重大学 教員紹介ページ
・Wikipedia「藤田達生」
・各種講演・著書インタビュー記録