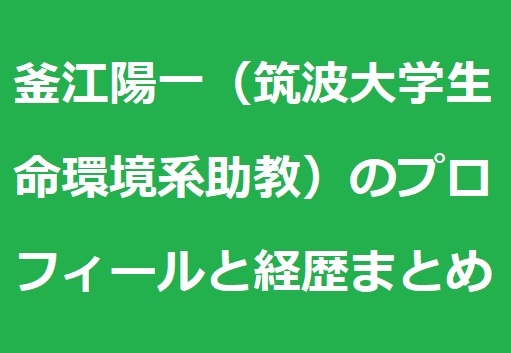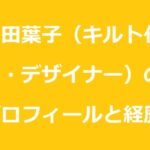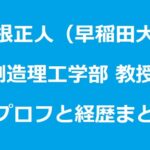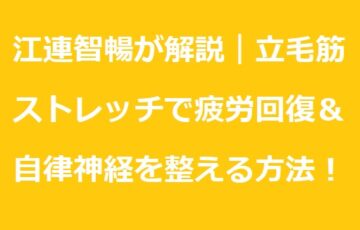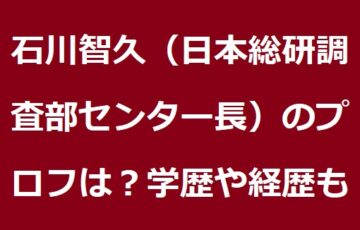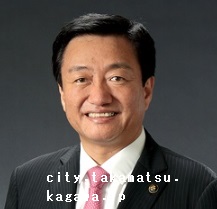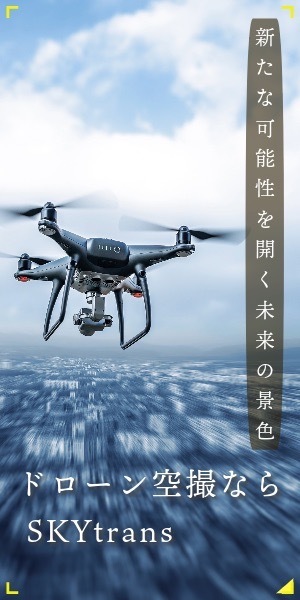Table of Contents
釜江陽一 プロフィール・経歴まとめ(筑波大学 生命環境系 助教)
プロフィール
-
名前(よみ):釜江 陽一(かまえ よういち)
-
役職・所属:筑波大学 生命環境系 助教、KAMAE Lab. on Climate Variability and Change 主宰
-
取得学位:博士(理学・筑波大学、2012年)
-
専門分野:大気科学、気候力学、総観規模の気候変動と異常気象(特にAtmospheric Rivers/大気の川)
🧭 経歴:国内外を舞台にした研究活動の歩み
学歴・初期キャリア
-
2003〜2007年:筑波大学で学士課程修了
-
2007〜2009年:同大学大学院修士課程在籍
-
2009〜2012年:博士後期課程修了し、博士号取得(理学)
研究職・客員研究員としての展開
-
2012〜2013年:東京大学 大気海洋研究所所属、研究員として公募研究に携わる
-
2013〜2015年:国立環境研究所 大気海洋研究センターで研究員として活動
海外滞在と国際共同研究
-
2015年4月〜2017年8月:米国・カリフォルニア大学サンディエゴ校スクリプス海洋研究所にて客員研究員として滞在。大気の川(Atmospheric Rivers)研究を世界的にリードする研究者と共同研究
筑波大学での現職(2015年〜現在)
-
2015年4月より現職。気候変動や異常気象現象を専門とし、研究室を主宰
🔬 主な研究テーマと知見
🌧️ 大気の川(Atmospheric Rivers)と極端降水の研究
-
日本および東アジアにおいて「大気の川」がもたらす極端降水とその発生メカニズムを精緻に解析。地形影響やENSOとの関係性にも踏み込んだモデル検証を実施
-
2024年には、もたらす豪雨の地域分布や強度特性に関する重要研究を多数発表
☁️ 気候感度と雲フィードバックの解析
-
温暖化下での雲の挙動と大気雑音応答(気候感度)を数値モデルで追究。雲調整(cloud adjustment)による不確実性低減の研究で、アジア・オセアニア地球科学学会などで講演
🧪 古気候モデリングと中緯度気候変動の探究
-
Pliocene(鮮新世中期)など過去気候を再現する古気候モデリングに取り組み、氷河期や東アジアのモンスーン系に影響を与えた気候動学との連携研究も実施中
🎖️ 受賞・社会貢献:研究成果と評価
-
日本気象学会 正野賞(2023年):大気大循環と大気の川の間の速い気候変動メカニズムの解明
-
日本気象協会 岡田賞(2023年):東アジアにおける極端降水現象の地理的影響を科学的に明らかにした功績
-
筑波大学 若手教員奨励賞(2024年11月):教育と研究の両面での貢献を評価
📚 主な業績・著作
-
主査読論文例
-
Atmospheric Rivers Bring More Frequent and Intense Extreme Rainfall Events Over East Asia Under Global Warming(Geophysical Research Letters, 2021)
-
日本で発生する相対的に強い降水に占める大気の川事例の割合(天気、第69巻11号、2022年)
-
-
共著・図書
-
ニュース・天気予報がよくわかる気象キーワード事典(ベレ出版、2019年)など多くの一般向け気象用語集に寄
-
🌐 社会との接点と今後の展開
-
大気変動観測データや遠隔影響パターンを使った大気の川のデータセット構築プロジェクト(2025–2027、科研費基盤(C))を研究代表者として主導
-
また、北極寒気の中緯度移行やモンスーン変動に関する基盤Aプロジェクトにも参画し、気候変動予測の不確実性低減に挑むチームの一員に
-
学部・大学院の教育では「Atmospheric Sciences」や「気候変動科学ゼミ」などを担当し、未来の気象研究者育成にも注力中
こちらの記事も読まれています!
📝 総まとめ:釜江陽一 先生とは?
釜江陽一先生は、「大気の川」という極端降水現象を中心に、地球温暖化と気候変動の影響を多面的に探究する若手気象学の旗手です。国内外での客員研究、国際会議での講演、学会賞受賞など、その研究の質と影響力はますます高まっています。
社会全体に深刻な被害をもたらす極端気象や豪雨災害を、科学的に「見える化し」「予防」する取り組みを通じ、気象学の現代的使命を体現する存在です。