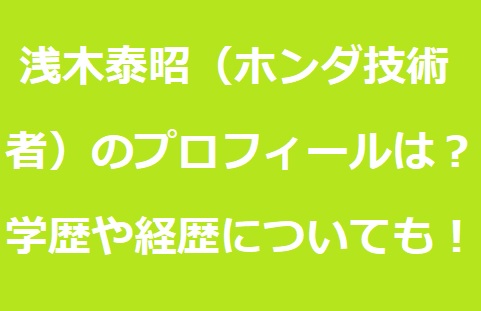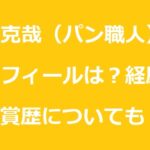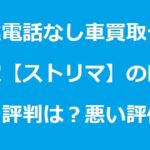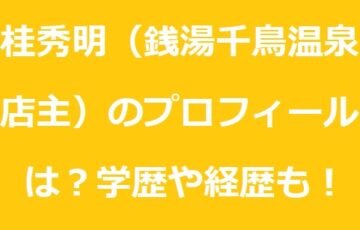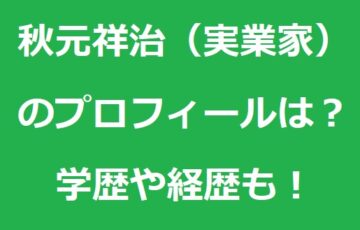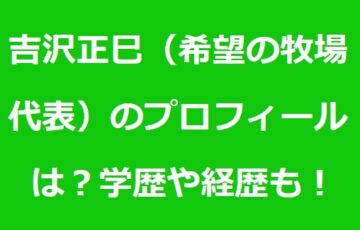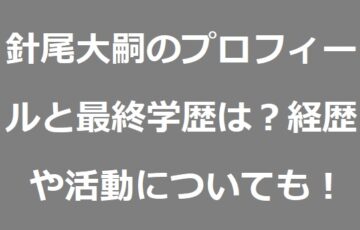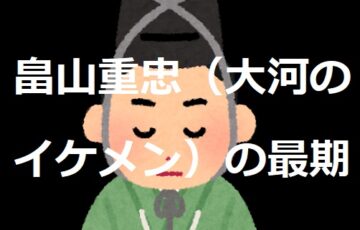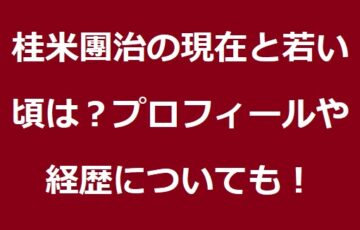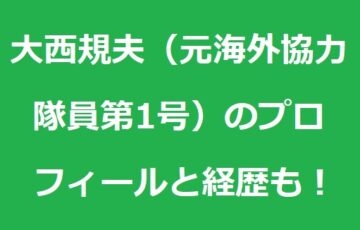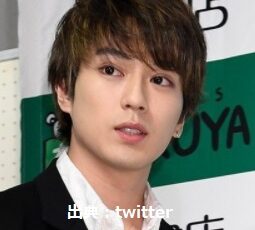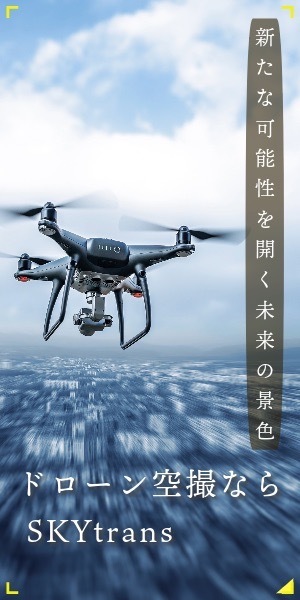4月5日の「新プロジェクトX」に、浅木泰昭さんが出演!
浅木泰昭さんってどんな人なのか気になり調べてみました。
今回は、『浅木泰昭(ホンダ技術者)のプロフィールは?学歴や経歴についても!』
というタイトルで、浅木泰昭さんについてお伝えしたいと思います。
どうぞ最後までごゆっくりお読みください。
Table of Contents
浅木泰昭(ホンダ技術者)のニュース

出展:NHK
新プロジェクトX〜挑戦者たち〜 走れ 挑戦の魂〜F1 30年ぶりの世界一〜
世界最速のレース「F1」で日本のメーカーが30年ぶりのチャンピオンを獲得。
日本のものづくりの意地を見せつけたのは、定年間際の伝説の男と若き技術者たちだった。
4月5日 土曜 20:00 -20:50 NHK総合1・東京
番組内容
1960年代、創業者本田宗一郎が挑んだのを皮切りにはじまったF1への挑戦。
80年代にはアイルトン・セナを擁して最強を誇ったが、
その後、沈みゆく日本のものづくりを象徴するように凋落していた。
30年ぶりの復活を遂げた立役者は新世代の技術者たちと、
日本一売れる軽自動車を開発した「伝説の男」。
世代をこえてぶつかりあいながら大逆転を果たした技術者たちの、
夢と挑戦の物語を秘蔵映像をまじえて描く。
出演者
【出演】浅木泰昭,
【語り】田口トモロヲ
引用:「新プロジェクトX」の番組案内から
浅木泰昭(ホンダ技術者)のプロフィール

出展:JBpress
浅木泰昭(あさき やすあき)さんは、日本の自動車技術者であり、特にホンダの名車「NSX」の開発責任者として知られています。長年にわたりホンダに在籍し、エンジニアとして数々の名車開発に貢献してきたレジェンド的人物です。
名前:浅木泰昭(あさき やすあき)
年齢:1952年生まれ(2025年現在で73歳)
出身地:長野県佐久市出身
最終学歴:東京大学工学部 機械工学科 卒業
職業:元ホンダ技術者
1975年に本田技研工業へ入社。初期はCVCCエンジンの開発に携わり、その後F1プロジェクトやプレリュードなどの車両開発にも参加。そして1990年に発売された初代NSXでは開発責任者として、世界初のオールアルミモノコックボディ量産車という革新的な挑戦を成功させました。
その後も数々のホンダ車の開発に携わり、2000年代には技術研究所の所長を歴任。ホンダのエンジニアリングスピリットを体現する存在として、若手技術者にも多くの影響を与えています。
現在は大学で講演活動を行ったり、クルマ関連のイベントにも登壇するなど、次世代に技術と情熱を伝える活動にも精力的です。
浅木泰昭さんのの経歴

出展:Car Watch
【第1章】ホンダを支えた天才技術者・浅木泰昭とは?
「N-BOXの父」と呼ばれた男、浅木泰昭(あさき やすあき)。
その名前は、クルマ好きであれば一度は耳にしたことがあるかもしれません。
しかし、彼がどれだけの情熱と挑戦をもってホンダという企業、
そして日本の自動車技術に貢献してきたかを知る人は、意外と少ないのではないでしょうか?
浅木さんは1958年、広島県に生まれました。
大学では機械工学を専攻し、1981年に本田技研工業(ホンダ)へ入社。
配属先は本田技術研究所。
ここから、約40年以上にもわたる熱いエンジニア人生が幕を開けます。
彼の歩みはまさに「挑戦」と「改革」の連続でした。
新卒で入社した翌年には、早くもF1エンジンの開発チームに抜擢。
まだ若かった彼は、先輩たちの開発方針に疑問をぶつけ、
自分の意見を貫き通す強い信念を持っていました。
それが評価され、次々と重要なプロジェクトを任されるようになります。
この記事では、浅木泰昭さんのこれまでのキャリア、情熱、
そして彼が作り上げた数々の名車について、徹底的に掘り下げていきます。
きっと、ホンダ車に込められた“魂”がもっと感じられるようになるはずです。
【第2章】F1エンジン開発に挑んだ20代の若者
1981年にホンダに入社した浅木泰昭さんは、本田技術研究所に配属され、
まずはエンジンテストチームの一員としてキャリアをスタートさせました。
ところが翌1982年、彼は驚くべきスピードでF1エンジン開発チームに異動します。
当時のホンダF1といえば、まだ「第2期」として再挑戦しようとする黎明期。
技術者も少なく、開発環境は非常にハードだったそうです。
浅木さんは「当時、F1エンジンのテストをしていたのは自分と上司の2人だけだった」
と語っています。
まさに手探り状態。
そんな中で彼は、RA163Eという極端なビッグボア・ショートストロークエンジンに
疑問を抱き、「ボアサイズが大きすぎる」と真っ向から反対。
若手ながらも、遠慮なく上司に食ってかかる姿勢は、
まさに“技術バカ”の本領発揮と言えるでしょう。
とはいえ、当時の先輩たちは彼を疎ましく思うどころか、「あいつ、面白いな」と
居酒屋に連れて行ってなだめるような温かい雰囲気もあったそうです。
そんな環境の中で、浅木さんは技術とチームワークのバランスを学びながら、
自動車エンジニアとして急速に成長していきます。
このF1プロジェクトでの経験が、後に彼が手がける数々の市販車、
そして再び挑むF1開発にも大きな影響を与えていくことになります。
【第3章】市販車開発で輝いた“逆張りエンジン”の哲学
F1の開発現場で鍛えられた浅木泰昭さんは、その後市販車開発へとフィールドを移します。
彼が関わったプロジェクトの中でも特に知られているのが、軽自動車「ライフ」や
「ゼスト」、そして伝説的な「N-BOX」シリーズの開発です。
これらの車は、単なる“足代わりのクルマ”ではなく、「走って楽しい」「燃費がいい」
「室内が広い」など、多くの要素を高い次元でバランスさせた名車ばかりでした。
特に注目すべきは、浅木さんが打ち立てた“逆張りエンジン”という哲学です。
たとえば、ライバルメーカーが燃費改善のためにエンジン回転数を抑える中、
浅木さんは「むしろ高回転型のほうが、実用域でのレスポンスが良い」と判断し、
あえて高回転寄りのエンジン設計を推進しました。
また、当時の軽自動車業界では「三気筒」が常識だった中、
浅木さんはあえて四気筒エンジンを採用したプロジェクトもありました。
「エンジンのバランスが良く、スムーズに回る四気筒がドライバーの満足度を高める」
という、エンジニアとしての美学がそこにはありました。
これらの決断は一見“逆張り”に見えるかもしれませんが、すべては「ユーザーの感動体験」を
最優先に考えた結果なのです。
技術に対して妥協をしないその姿勢は、彼の開発するクルマたちにも如実に現れ、
多くのファンを魅了する理由のひとつとなりました。
【第4章】N-BOX誕生と“軽の常識”を覆した革命
2011年、ホンダは「N-BOX(エヌボックス)」を発表します。
今では軽自動車の代名詞とも言えるこのモデルも、実は浅木泰昭さんが総責任者として
ゼロから創り上げたプロジェクトでした。
この車の開発には、浅木さんの“逆張り哲学”と“エンジニア魂”が全力で注ぎ込まれています。
当時、軽自動車は「安くて小さくてそこそこ走ればいい」という認識が強かった時代。
しかし浅木さんは、「日本の家族が本当に求めているのは、安全で快適で、
子どもや高齢者にも優しい“暮らしの道具”」だと考えていました。
だからこそ、N-BOXは徹底して“人のため”に作られた軽自動車だったのです。
たとえば、後席のスライドドア。
小さな子どもを抱えたママでもワンタッチで開閉できるよう工夫されており、
車高は高めで、足腰の弱い高齢者でも乗り降りしやすくなっています。
また、室内空間はまるでミニバン並みの広さ。
軽自動車でありながら、ライバル車と一線を画す快適性を実現しました。
もちろん、燃費性能や安全性能にも妥協はなし。
軽量化のための徹底的なパッケージ設計や、衝突安全ボディ「G-CON」など、
ホンダの最新技術を惜しみなく注ぎ込んだのも浅木さんの判断です。
結果として、N-BOXは発売から数年で「日本一売れているクルマ」に成長。
しかもその記録は何年も継続され、軽自動車というカテゴリの枠を超えて、
日本の自動車史に名を刻む存在となりました。
浅木さんはこの成功に驕ることなく、
「N-BOXはホンダが“社会のためにできること”のひとつ。
使う人が笑顔になれる車が、やっとできたと思いました」と語っています。
次の【第5章】では、
浅木氏がホンダ社内で貫いた“開発者の哲学”について深掘りしていきます。
【第5章】開発者として貫いた“人ありき”の哲学
浅木泰昭さんの仕事ぶりを語るうえで欠かせないのが、
彼が常に貫いてきた「人ありき」の哲学です。
彼の開発スタイルは、データや理論に基づいた技術の追求はもちろんのこと、
「そのクルマに乗る人の幸せ」を常に中心に据えていた点が特徴です。
たとえば、開発初期の段階から現場の声を徹底的に聞き込み、営業マンや販売スタッフ、
整備士、そして実際のユーザーまでも巻き込んで意見を取り入れる姿勢は、
技術者という枠を超えてまさに“プロダクトマネージャー”的な視点を持っていたと言えます。
そして何より、浅木さんが一貫して守ってきたのは「お客様にウソをつかないクルマ作り」。
燃費や加速性能、快適性など、どんな要素も“スペック上でよく見せる”のではなく、
“日常の中でどれだけ信頼されるか”を最重視していたのです。
特に印象的なのは、
「数字はウソをつかない。でも、使い方次第でウソのように見えることもある」という言葉。
これは、技術者が陥りがちな「スペック至上主義」への警鐘でもあります。
浅木さんの哲学は、クルマという工業製品を「人と社会をつなぐ道具」と捉え直すきっかけを
多くの開発者にもたらしました。
だからこそ、彼が関わったクルマには“ぬくもり”や“優しさ”が宿っていると、
多くの人が口をそろえて語るのです。
【第6章】若手への想いと“後進育成”への情熱
浅木泰昭さんのキャリアを語るとき、決して外せないのが「若手育成」にかけた情熱です。
F1エンジン開発の若き日、上司たちに自由な発言の場を与えられた経験が、
彼自身の中で強く根付き、のちのち“次世代の育成”というミッションにも
つながっていきました。
特に2000年代以降、彼が率いたNシリーズや軽自動車の開発現場では、
若手技術者が多く起用されていました。
それは単に「若い力に任せてみよう」というものではなく、
「現場で揉まれなければ本当のクルマは作れない」という、
浅木さんなりの教育方針だったのです。
たとえば、ある開発ミーティングで「この仕様は現実的ではありません」と
意見した若手に対して、浅木さんは
「だからこそやるんだよ。技術者が“現実”で止まったら、何も変わらない」と
返したというエピソードも残っています。
まさに“夢と現実の狭間をつなぐのが技術者”という信念が表れた瞬間です。
また、浅木さんは講演会や社内勉強会にも積極的に登壇し、
「どうやって“お客様の心を動かすクルマ”を作るか」というテーマで
熱く語っていたそうです。
その姿に感化された若手は数知れず、今やホンダの中心的開発メンバーの中には、
彼の“背中”を見て育った人が多数存在しています。
浅木さんの若手育成は、単なる技術継承にとどまりませんでした。
「志」と「お客様への誠意」、そして「ぶれない芯」をどう持ち続けるか。
そうした“生き方”まで伝えていった稀有なエンジニアだったのです。
【第7章】“ホンダの魂”を宿した男の功績とこれから
浅木泰昭さんは、ホンダという企業の技術と精神の両面を象徴するような人物です。
F1から軽自動車まで、スケールもジャンルも超えて活躍してきたその足跡は、
まさに“ホンダの魂”そのものと言えるでしょう。
技術者として常に「人のため」に技術を磨き、時には逆風の中でも信念を貫き、
地味な軽自動車というジャンルに革命を起こしました。
彼が手がけたクルマたちは、今もなお多くの人の日常に寄り添い続けています。
そしてもうひとつ、浅木さんが残した大きな功績は、
“技術者の在り方”そのものを次の世代に伝えたことです。
スペックや見た目だけではない、本質を見極め、人の感情に訴えかけるモノづくり。
それを可能にする「覚悟」と「誠実さ」が、彼の背中から今も語りかけてくるようです。
現在、第一線を退いたあとも浅木さんは講演活動やメディアを通じて、
後進の技術者やクルマ好きに向けてメッセージを発信し続けています。
クルマは道具であると同時に、「人と社会を笑顔にする存在」でなければならない。
その信念が、これからも多くの人の心に火を灯していくでしょう。
こちらの記事も読まれています!
まとめ:浅木泰昭という技術者の“人間力”
F1の世界に飛び込み、地道な実験と失敗を重ねながら夢を形にしていった青年。
市販車開発で“逆張り”の選択を貫き、数々の名車を世に送り出してきた中堅エンジニア。
そして今、ホンダの歴史と精神を後進に託し続ける“師匠”として。
浅木泰昭さんの人生は、技術者であると同時に「人間として、どう生きるか」を教えてくれる
壮大なストーリーです。
派手さではなく、誠実さ。効率ではなく、感動。そんな価値観に立脚したモノづくりが、
これからの時代にこそ求められているのかもしれません。
私たちが何気なく乗るクルマの中にも、こうした“誰かの信念”が宿っている。
その事実を思い出すだけで、日常の景色が少し違って見えてきませんか?
今回も最後までお読みいただき有難うございました。