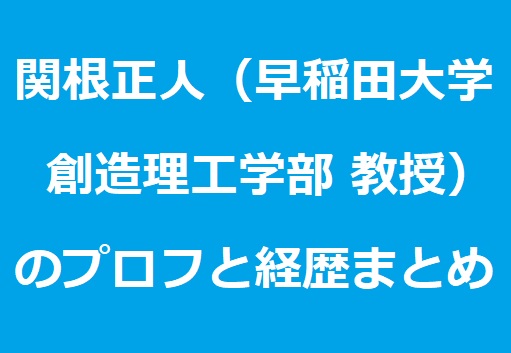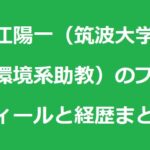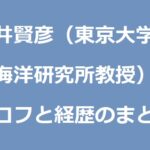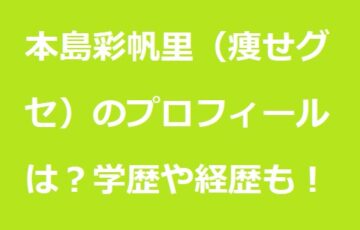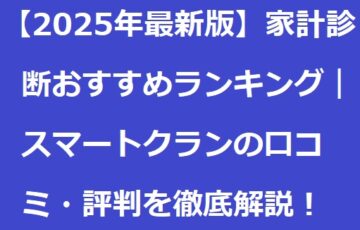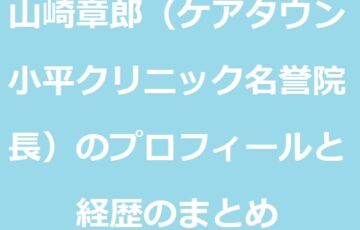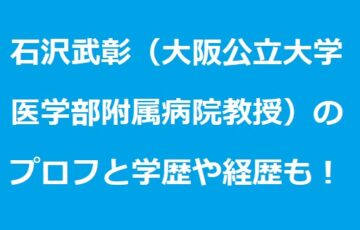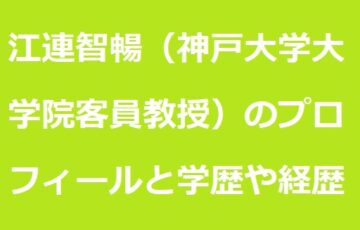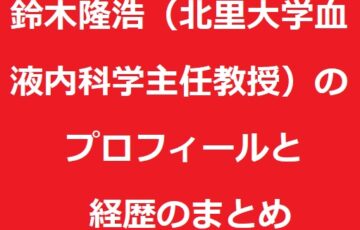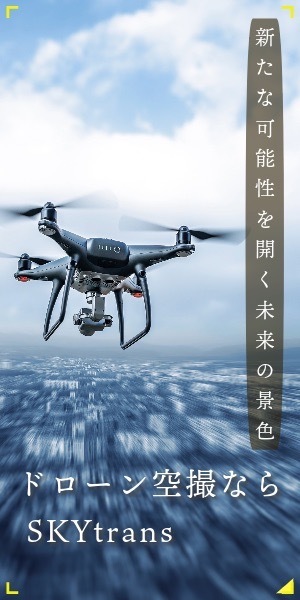Table of Contents
関根正人 プロフィール・経歴まとめ(早稲田大学 創造理工学部 教授)
プロフィール
-
名前(よみ):関根 正人(せきね まさと)
-
職名・所属:
-
早稲田大学 創造理工学術院 社会環境工学科 教授(創造理工学部/大学院建設工学専攻)
-
-
学位:工学博士(早稲田大学 大学院・理工学研究科 建設工学専攻、1988年3月)
-
専門分野:河川工学・水理学・都市防災工学、水害・河道形成・洪水予測および避難誘導に関する研究
-
生年月日・出身地:1959年12月生まれ(埼玉県出身)
🧭 経歴:早稲田大学における研究と教育の歩み
初期キャリア(1980年代〜1993年)
-
1986年4月:早稲田大学理工学部土木工学科 助手
-
1988年:博士課程修了後、University of Minnesota St. Anthony Falls Hydraulic LaboratoryにてPost‑doctoral Research Fellowとして研究を継続
-
1991年:科学技術庁・建設省 土木研究特別研究員を経験
-
1992〜1994年:専任講師・助教授としてキャリアを積み、2000年4月から教授に昇進
教授就任以降の研究・指導(2000年〜現在)
-
2000年:理工学部教授に就任、2003年の学部改組により社会環境工学科へ異動
-
専門は河川流動システムや砂礫モデル、都市域浸水予測、避難誘導など → 実務的にも学術的にも重要な研究をリード
🔬 主な研究テーマと成果
1. 洪水・浸水予測と都市防災システム
-
都市の地下空間や地下街も想定した**リアルタイム浸水予測システム「S‑uiPS」**を研究開発。豪雨時の避難誘導技術向上に寄与
-
東京23区や横浜・川崎など都市部の浸水危険性を具体的にモデル化し、社会実装に取り組む研究が進行中
2. 河床変動と流砂理論の再構築
-
粘着性土や多粒径砂礫を対象とした数値流砂モデルの開発。扇状地・砂堆形成過程における粒子運動解析を実践し、地形形成の機構を解明
-
河道の自律形成機能とその予測技術を構築し、河川維持管理や治水政策への応用を目指す
3. 河川堤防決壊メカニズムの解明
-
浸透・越水によって起こる堤防破壊のプロセスを数値モデル化。内水氾濫や避難設計に必要な基礎データの提供を追求
-
内水氾濫危険性評価と都市避難誘導の戦略研究にも取り組んでおり、実務現場とのリンクが強いテーマ
🏆 学会・社会的貢献と受賞歴
-
土木学会 水工学論文賞 を2004年・2015年・2016年に受賞
-
土木学会水工学委員会 幹事長(2009〜2011年)や論文編集委員長、IAHR日本支部理事などを歴任し、国内外で制度設計・技術普及に貢献
-
国土交通省や自治体の防災関連委員なども多数務め、実社会への技術応用を積極的に推進
📚 著書・教育活動
-
著書
-
『移動床流れの水理学』(共立出版、単著、2005年)
-
『水理公式集』(共著、土木学会)
-
『砂防用語集』(共同執筆)
-
『土木技術検定試験 問題で学ぶ体系的知識』(共著)
-
-
教育
-
学部・大学院で河川工学、水理学、防災工学を指導。数多くの卒業設計・修士論文指導実績あり
-
実用的社会課題に基づいた演習プログラムも提供
-
こちらの記事も読まれています!
📝 総まとめ:関根正人教授とは?
関根先生は、数理モデルとフィールド観測を融合させた実践型水理学者であり、都市間洪水や浸水被害の予測システム、避難誘導技術、砂礫地形形成などを体系的に研究してきました。技術・政策・市民の橋渡し役としての立場も兼ね備え、**研究と社会貢献を両立する「現場型技術者」**です。
今後も豪雨・洪水リスクが増す社会において、関根教授の研究成果は防災・都市計画・環境技術の基盤として重要性を増していくことでしょう。